| World > Africa > Mali | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Artist | ||||||||||||||||
|
SALIF KEITA / LES AMBASSADEURS INTERNATIONAUX |
||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
|
MANDJOU |
||||||||||||||||
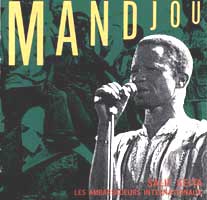 |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Review |
||||||||||||||||
| サリフ・ケイタがおもしろくない! わたしが、いわゆるワールド・ミュージックの世界へズブズブのめり込んでいくきっかけをつくってくれたのが、87年にサリフ・ケイタがリリースした"SORO"(MANGO CCD9808(US))だった。鋼のように強靱でムチのようにしなう堂々たるヴォーカル、アフリカの伝統文化に根ざしためくるめくポリリズム、それらと最新のエレクトロニクスとの出会いから生まれた音楽は、ロックの終焉を予感させるに十分な衝撃度があった。サリフの音楽を知ってしまった耳には、ロックがなんと単調に聞こえたことか。 続いて89年にリリースされた"KO-YAN"(MANGO C1DM1002(US))も、前作の路線をさらに推し進めたつくりになっていて、わたしの期待に十分に応えるものであった。ところが、ジョー・ザヴィヌルがプロデュースした91年の第3作"AMEN"(MANGO 162 539 910-2(US))は、音がスカスカになって手応えがまったく感じられず、ひどくガッカリさせられた。 しかし、4年間の沈黙ののち、95年に発表された"FOLON"(マーキュリーPHCR-1804(JP))は、「過去」を意味するタイトルが示すとおり、みずからの原点に立ち返りながら、パン・アフリカニズムを指向した充実作であった。 その後、ジャズの名門ブルーノートに移籍し、元リヴィング・カラーのヴァーノン・リードを共同プロデューサーに迎えて、99年に"PAPA"(METRO BLUE 7243 4 99070 2 7(FR))を発表。基本的には前作の延長線上にあり、世間でいわれるほどには悪い出来とは思わなかったが、ひっかかるところがなかったのも事実。曲づくりといい、人選といい、ついでにいえばブルーノートに所属したことといい、時代的な必然性がまったく感じられない凡作だった。 そういう意味で、先ごろ発表されたばかりの最新作"MOFFOU"(ユニバーサル UCCM-1035(JP))は、全編アコースティックによる、一皮むけて円熟の境地に達した意欲作。はじめて聴いたときは結構イケルと感じたが、3回ぐらい聴いたら飽きてきた。カンテ・マンフィーラといい、ロキア・トラオレといい、ここ数年来、アコースティック路線が大はやりだが、どれも“いやし系”のにおいが漂ってきて、どうにも居心地が悪い。サリフも例外ではない。 サリフのアルバムはぜったいに落とすことはできないのだけれども、当時は大感動した"SORO"にしても、"KO-YAN"にしても、いま聴くとエレクトロニクスを駆使した仰々しいプログレ的な展開に寒いものを感じてしまって、とてもこのコーナーでとりあげる気にはなれなかった。かといって"FOLON"は、いいアルバムだとは思うのだが、いまひとつ決め手を欠いている気がする。 このままではサリフという類まれな才能が、リスナーの嗜好に応じて千変万化しつづける“ワールド・ミュージック”に骨の髄まで喰い尽くされてしまう。すでに盛りは過ぎたと思っていたユッスー・ンドゥールが、セネガルにある自己のレーベルから発表した新作"BA TAY"で、原点に立ち返ったストレートなンバラを聴かせ、大いに健在ぶりを示してくれたように、サリフもここらでもう1度、コアなマンデ・ポップの作品をつくるべきではないか。 そんなわけで悩みに悩んだあげく、ここではサリフが"SORO"ではなばなしく世界デビューする前の、アンバサドゥール時代の録音をとりあげることにした。 サリフのミュージシャンとしてのデビューは、1970年、首都バマコの駅にある国営ホテルの専属バンド、レイル・バンドであったが、印税をめぐって仲間と折り合いが悪くなって、73年には“レ・ザンバサドゥール・デュ・モテル・ドゥ・バマコ”(以下、アンバサドゥール)へ移籍する。 アンバサドゥールは、その名がしめすとおり、おもに外国人や上層階級むけのバマコに近い国営モテルの専属バンドとして、69年に結成された。バンドは、「アンバサドゥール」(大使)の名にふさわしく、コート・ジヴォワール人、ギニア人、ガーナ人、ナイジェリア人などからなる多国籍編成だった。71年、ギタリストとして、マンディングのグリオ出身でギニア人のカンテ・マンフィーラが加入。77年には、リズム・ギターにギニア人のウスマン・クヤテが加わり、ここに鉄壁のラインナップが出揃った。結成当初は、ジャズやラテンをおもなレパートリーにしていたアンバサドゥールだったが、サリフを含むかれらの加入により、アフリカの伝統色をつよめていった。 そんなかれらがコート・ジヴォワールの貿易都市アビジャンに拠点を移したのは78年8月のこと。市内にあるマンディングのコミュニティに身を寄せながら、不遇の日々を送っていたかれらにレコーディングの機会が巡ってきたのは、それからおよそ1年後のことであった。 国営テレビ局のエンジニアが局から無断で持ち出した録音機材を使って、わずか2時間で録り終えたアルバムこそ、マリ音楽史上に輝く傑作として名高い"MANDJOU"であった。77年にサリフが作曲した表題曲'MANDJU'は、ギニア大統領セク・トゥーレを讃えた歌。この曲は西アフリカ全域で大ヒットを記録し、気をよくしたかれらは翌年、グループ名を“レ・ザンバサデュール・アンテルナショノー”とした。 この年、メンバーのうち、サリフ、マンフィーラ、ウスマン・クヤテ、それにドラムス?のムサ・シソコの4人はレコーディングのためアメリカへ渡った。残りのミュージシャンは、現地調達したが、そのときのキーボード奏者にアメリカ留学中のコンゴのミュージシャン、レイ・レマがいた。こうして幾多のトラブルに巻き込まれながらも、かれらはアメリカ滞在中の3ヶ月間に2枚のアルバムをものにすることができた。ここからシングル・カットされた'PRIMPIN'は大ヒットを記録し、かれらは人気を不動のものとしたかにみえた。しかし、82年、サリフはアンバサドゥールを脱退。翌年、単身パリへと渡った。そして、パリへ渡って4年後の87年、サリフはソロ・アルバム"SORO"をひっさげて、われわれの前に彗星の如く登場するのだが、この間、異国の地にあって、サリフがなにを思い、なにをしていたのかわたしは知らない。 さて、95年にサリフ・ケイタの来日(3回目ぐらいかなあ)に合わせてメタ・カンパニーより国内発売された本盤には、79年のアルバム"MANDJOU"全5曲のうち、表題曲を含む3曲、アメリカ録音の2枚のアルバムから5曲が選ばれている。約68分と収録時間がたっぷりあるのがうれしい。日本独自編集盤だと思っていたが、現在は廃盤になっている"SALIF KEITA 69-80"(SKD/SONODISC CD74646(FR))と同一内容であることを最近になって知った。 ほかにも"LES AMBASSADEURS INTERNATIONALES WITH SALIF KEITA"(ROUNDER 5053(US))と、(わたしはフランス盤で持っているが以前メタ・カンパニーより国内発売されていた)"SEYDOU BATHILY"(SONODISC CDS7004(FR))などがあるが、本盤との重複曲はほとんどなく、したがってかれらの代表曲である'MANDJOU'と'PRIMPIN'が聴けるのは本盤だけ。 アンバサドゥールは、サリフのヴォーカル、カンテ・マンフィーラのリード・ギター、ウスマン・クヤテのサイド・ギターに、サックス、トランペット、オルガン、ベース、ドラムス、コーラス、それにバラフォンを加えた編成。ギニアのベンベヤ・ジャズの影響を受けているといわれるが、ベンベヤよりも軽快で明るくあか抜けた印象を受ける。時代のせいもあろうがラテン・フレイヴァーはあまり感じられず、むしろロックやジャズ寄りのサウンドだ。 レイル・バンド時代から格段にうまくなったサリフのヴォーカルは、現在よりも声のトーンが高く、とくに高音部でのちからづよい声のノビがすばらしい。ソロ・デビュー後のサリフは、カリスマ性を帯びた声のあまりの迫力にときに圧迫感があったが、ここではじつにのびのびとしていて押しつけがましさがまったくない。なかでも、"FOLON"でも再演された12分36秒に及ぶ'MANDJOU'は、サリフ屈指の名唱といえる。ブルース調のレイジーなムードをもつこの曲で、ひときわ目立っているのはクールなギター・ソロを聞かせるカンテ・マンフィーラと、ジミー・スミスのニックネームで呼ばれていた“スミス”が奏でるブルージーなオルガン。「サマータイム」のフレーズが飛び出すマイルス風のミュート・トランペットもかっこいい。 また、本物のバラフォンをバックに、マンフィーラとウスマン・クヤテが奏でるめくるめくギター・アンサンブルも、コンゴやギニアにはない独自の硬質で乾いた音色を醸し出していて興味ぶかい。 'MANDJOU'にかぎらず、'PRIMPIN'は"KO-YAN"で、'N'TOMAN'は'N'BIFE'として"AMEN"で、というように、サリフは過去の曲をソロ・アルバムでリメイクしているケースも少なくないけれども、洗練度は増してもパワーの点でやはりオリジナルの足元に及ばない。 それにしても、新作"MOFFOU"のように、なにも全面アコースティックにせずとも、せめてホーン・セクションを全員アフリカのミュージシャンにして、シンセの打ちこみをバラフォンに換えるだけでも、アンバサドゥール時代のような音の深さと味わいは出てくるとは思うのだが‥‥。 |
||||||||||||||||
|
(5.20.02) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
前の画面に戻る |
||||||||||||||||